 |
�Ɛ��w�� |
�X�V 2013�N7��29��
���ӁF���ɂƐH�i�̊W�͌l�����傫�����̂ł��B
���{�l�͐H�i�ɓ݊��̂悤�ł��B
���܂�_�o���ɂȂ�Ȃ��悤�ɂ��肢���܂��B
���������ɂ̐f�ÃK�C�h���C���̎w�j�ɂ͂ǂ̂悤�ɏ�����Ă��邩
- �����������ȓ��Ɂi�H�i�̖��O���������Ɂj
- ���ጌ���ɂ�铪���i���H�A���H�����͓��ɂ̌����ƂȂ�j
- ���_�C�G�b�g����
- ���r�^�~���`�̐ۂ�߂��͓��ɂ̌����ƂȂ�B
- �H�i�A�����M�[
- �`���R���[�g
- �����Ɠ��ɂƂ��ɂԂǂ����Ɠ��ɂ̊W
- ��������̓��ɂ͂Ȃ�������̂ł����B�y�ɂȂ���@�͂���܂���
- ���x
- �A���R�[�������Z�x�̐���
- ���Ƀp���h�b�N�X
- ��������Ƃ�
- ������������ɂƕГ��ɂɋ��ʂ̏Ǐ�
- �����̈��߂�l�A�t���Ȃ��l�̍�
- ���������߂Ȃ��l���P���ň��߂�悤�ɂȂ���Ė{���H�������݂͖����������Ȃ��Ȃ���Ė{���H
- �A���R�[���̓K��
- �K�������̂P�O�J��
- �J�t�F�C���͓��ɂɂ悢
- �J�t�F�C���֒f���ɂ̍��ۓ��Ɋw���`
- �J�t�F�C���ˑ�������
- �J�̓J�t�F�C�����炯�ł�
- �J�t�F�C���֒f������
- �e������A��܂̃J�t�F�C���ܗL��
- �J�t�F�C���̐ۂ�߂��͓��ɂ̂ق��Ɂu�߂܂��v�̌����ɂ��Ȃ�܂��B���Г��ɗU��
- �J�t�F�C���֘A��Q�@Caffeine-related Disorders
- ���������Ɂ`�J�t�F�C���������͒��ɖ�̃��o�E���h���ɂ�52.5��
- �J�t�F�C���̍�p�@��
- �R�[�q�[�̂����v
- ���ɂɌ������V�s�� http://www.toku-chi2.com/health/recipe/bn_04
- �J�t�F�C���̐ۂ�߂������ɁE�߂܂��̌�����-�ۂ�߂��ɋC��t���܂��傤
- �J�t�F�C���W����
- �Г��ɂ̗\�h�ɂ悢�}�O�l�V�E�������Ղ�̃n���o�[�O
- ���N�ێ��̂��߂̐H��
- �Г��ɂɂ悢�H�ׂ����i�}�O�l�V�E���Ȃǁj
- �H���Ö@�̌���Ł��Г��ɂ�MBT�ɂ�鎡��
- �����N���r�^�~���a2�Ö@�i�r�^�~���a�Q�̑�ʐێ�͕Г��ɂ����P������j�A
- �����N���i�c�V���M�N
- �����N���C�`���E
- L-�g���v�g�t�@��
- ����
- �����N���X�N����Q�̗\�h�ɐA�����G�X�g���Q����ێ悷��Ɨǂ��B
- �哤
- �R�J�E�R�[��
- �Г��ɂƏ�����Ǐ�
- ELH Spierings/���{����u�Г��ɂ̎��Áv1997���
- �n���E�\�[�Z�[�W�͓��ɂ̌����ƂȂ邩
- ���Ɏ_���E�Ɏ_��
- L-�g���v�g�t�@��
- ����
- ���H�K��
- �H���̐ێ�p�x
- ���Ƒ����������̂́H
���i�N�Г��ɂɔY�ޕ�����̌l�I�ӌ�
- �Г��ɂƐH�ו��̊W�A������ϋ^��ɂ������Ă���܂�
- �����g�A�`���R���[�g��`�[�Y�@����Ɋ��k�ޓ��Ł@�U�����ꂽ���Ƃ́@�Ȃ��Ǝv���Ă��܂�
- ���ȏ��I�ɂ́@�����Ȃ̂����m��܂��A
���Ȃ��Ƃ��@���{�̏Ƃ́@�����Ă��Ȃ��悤�ȁ@�C�����܂� - �Â����̂��ق����Ȃ�@�Ƃ����̂́A���̂Ƃ��@���Ɂ@�Г��ɂ��@�n�܂��Ă���̂���
�\���搶���@�������ɂȂ������̂��@�ǂL��������A
�����@���������ł͂Ȃ����Ɓ@�v���܂��� - ���̂Ƃ���Ɂ@�悭�d�b���Ă���l���A
�u�����ɊÂ����̂��H�ׂ��������̂ŁA
���낢��H�߂��Ă��܂�����A�Г��ɂ��n�܂�A
���ׂ�̂ł͂Ȃ������Ɓ@������Ă���v�Ƃ����܂��B - �u�C�������̂́@���̂����ł͂Ȃ����A
�䖝���Ă���A����ȓf���C�ɏP���邱�Ƃ́@�Ȃ������̂ł͂Ȃ����v�Ɓ@�����̂ł� - �ł����́A�u����͂������Ɂ@�\���������̂����m��Ȃ�����@�]�������āA
�䖝�ł��Ȃ������������@�ӂ߂Ȃ��ق��������v�ƌ����܂� - ���Ȃǂ��A����ɃA���R���H�ׂ����Ȃ�����
�P�[�L���~�����Ȃ����肵��
���̗����Ƃ��H�ׂĂ��܂����Ƃ�����܂� - �܂��n�܂�̂��Ȃ��Ɓ@���ȗ\�����o���Ȃ���A
���̂Ƃ��́@���������H�ׂāA���̌�@�����܂��������܂� - �����W����Ǝv���̂́@�A���R�[�������ł��B
������r�[������Ԃ悭����܂���B
��͂�@�ԈႢ�Ȃ��@���ǂ��g������Ȃ��@�Ǝv���܂� - (1999.12.05)
- ��top
���������ɂ̐f�ÃK�C�h���C��2013�N�ɂ͂ǂ̂悤�ɏ�����Ă��邩
- �H�i�ƕГ��ɂ̊W�ɂ��Ă̍l�����́A�������ɂ̐f�ÃK�C�h���C��2013�Ɏ��̂悤�ɏ�����Ă��܂��B
- �Г��Ɋ��҂̖�75%�ɉ��炩�̔���̗U�����q������B
- ��������퐶���̂Ȃ��Ŕ����邱�Ƃ͕Г��ɂ̗\�h�ɂȂ��邱�Ƃ���A
�X�̊��҂ɂ����邻�ꂼ��̗U�����q�|�������q��c�����Ă������Ƃ͏d�v�ł���B - �U�����q�Ƃ��Ă������Ă���H�i�͐��������A
���ׂĂ̊��҂ɂ��Ă͂܂�Ƃ������̂ł͂Ȃ��A
�܂����ꊳ�҂ł�����H�i�����ł����ɂ�U������Ƃ����킯�ł͂Ȃ��B - �A���R�[���ȊO�ɓ���̐H�i�������銳�҂͏��Ȃ��A
�ނ�݂ɐH�ו��𐧌����邱�Ƃ͂������Ċ��҂�QOL(�����̎�)��ቺ������ꍇ������B - ��top
�����ɂ̌����ƂȂ�H�i
- �Г��ɂ��A�ԂԂǂ����A�`���R���\�g�A�`�\�Y�ȂǂŗU�������̂͗L���ł�
- �Г��Ɋ��҂̂T�`�Q�T�����H�i�i�`���R���[�g�A�`�[�Y�A���C���A���k�ށj�ƊW������Ƃ���Ă��܂�
- �idietary migraine�Ƃ����܂��j
���Г��ɂ̌����ƂȂ�H�i�ꗗ
- �n���`�[�Y�^�����i
- �`���R���[�g
- ���k��
- ���b�ɕx�ސH��
- ��
- �ؓ�
- �A���R�[���i���C���A�V�����p���Ȃǁj
- �M�щʕ�tropical fruits�i�o�i�i�A�A�{�K�h�j
- �L���x�c
- �^�}�l�M
- �J�t�F�C���ܗL�����i�R�[�q�[�A�R�[���Ȃǁj
- ���Ђ��ɂ���
- �ۑ������i�i�z�b�g�h�b�N�A�x�[�R���A�T���~�j
- �{���o�[
- �ȏ�scope35(6):14-15�����p
- �ق��Ƀ��[�O���g�A�r�[���A���o�[�A�y��
- �H���Ɠ��ɂɂ��Ắˍ��ۋ��͕������ɂƐH�i�ɂ��ڂ���������Ă��܂�
- ��top
- �Г��Ɋ��҂͓��ɂɈ����ƕ��������ŁA�_�o���ɐH�ׂȂ��悤�ɂ��Ă���l���������̂ł����A
���ʂɕq���Ȑl�ȊO�́A�H�i�ɋC�ɂ�������̂́@�悭����܂���B - ���{�l�́A���m�l�قǁA�H���ɕq���ł͂Ȃ��悤�ł��B
- �������̎听���ł���O���^�~���_monosodium glutamate�����ɂ̌����ƂȂ�܂��B
- ���̂悤�ȓ��ɂ��A���ؗ����X�nj�QChinese restaurant syndrome�Ƃ����܂��B
- ���ؗ����́A���������ʂɎg���ꍇ������܂��B
- ��ʂ̃O���^�~���_�́A���ɂ⓮���̌����ƂȂ�܂� �B
- �q���Ȑl�͂R�O�����̃O���^�~���_�Ŕ��삪�N����܂��i�����^����t���j�B
- �H�ׂĂ���Q�O���`�R�O����ɂ�����āA�P���ԂقǑ����܂��B
- �̂Ƃ��Ɉ��ރO���^�~���_���܂ރX�[�v�����ɂ��N�����܂��̂ŁA
���ɂ��N�����₷���l�́A�O���^�~���_���܂܂Ȃ����̂��܂��H�ׂ�Ƃ悢�ł��傤�B
- �R�\�q�\�𑽈�����ƁA�J�t�F�C���֒f������caffeine withdrawal headache���������܂�
- ����ɑ���l�@�́��n���E�\�[�Z�[�W�͓��ɂ̌����ƂȂ邩
- �z�b�g�h�b�N��n���̖h���܂Ɏg�������Ɏ_�������ɂ̌����ɋ������Ă��܂� (�z�b�g�h�b�N�����j�B
- �����̐H�i�Ɋ܂܂��`���~���Ȃǁu���Ǎ쓮���A�~���v���A�����̌����ƂȂ�܂��B
- �`�\�Y��ԂԂǂ����́A�`���~��thyramine, �|���t�F�m�[���A�~��phenylthyramine�Ȃnj��Ǎ쓭���A�~�����܂ނ��ߕГ��ɂ�U�����܂� �B
- �ԃ��C���̕Г��ɗU���́A�����Z���g�j���̗V�����i��p�ɂ��Ƃ����������܂��B
- ��top
���`���R���[�g
- �`���R���[�g�͕Г��ɂ̗U���Ƃ��Ă��܂�ɂ��L���ł��B
- �������`���R���[�g�����Ƃ��錤���Ɣ��Ƃ��錤�������荬�����Ă��܂��B
- ���̌����ł͂܂������̔��ł͂Ȃ����̂́A�G��߂𒅂����Ă���A�Ƃ������Ƃł��B
- �����F�`���R���[�g�ێ�̓�d�ӌ��ɂ��Ɓu�Ɛl���v�͔ے肳�ꂽ�B
Blau JN. Migraine: Lancet 339:1202-1207, 1992 - ��������1�F�`���R���[�g�i��d�ӌ��jGibb CM, 1991
- ����F�v���Z�{=42���F0��
- ���ɔ��삪�N����܂ł̕��ώ��Ԃ�22���ԁi3.5�`27���ԁj
- �`���R���[�g�͐����w�I�A�~���ł�����\�t�F�G���`���~���𑽗ʂɊ܂�ł���B
- ���̃A�~���̓�-�A�h���i������e�̂��h������(GonsalvesA 1977. )
- ���O���̎��k�A���ʏ������A���������NJg���ɂ�铪�ɂ�������
- (ELH Spierings/���{����u�Г��ɂ̎��Áv1997���)
- Gibb CM, et al.: Chocolate is a migraine-provoking agent. Cephalalgia 11:93-5, 1991.
- ��������2�F Sandler��̒��펎��(chalenge study)�i1995�j
- �H�i�ێ��A���ɂ��N����̂�
- �`���R���[�g�@�@�@3.5�`27���� �i����22���ԁj
- �ԃ��C���@�@�@�@�@0.5�` 8���� �i���ςR���ԁj
- Sandler M, et al.: Dietary migraine: recent progress in the red (and white) wine story. Cephalalgia 15:101-3, 1995.
- �H�i�ێ��A���ɂ��N����̂�
- ��top
- �`���R���[�g�͕Г��ɂ̓G�̂悤�Ɍ����܂����A
- 11��4009�l�����Ń`���R���[�g�̍��ێ�Q�́A�S��������]�����Ȃǂ�3���O�㏭�Ȃ��Ƃ����������ʂ��A
BMJ�Ƃ����ɂ߂Č��Ђ̍�����w�G���ɔ��\����܂����B - (Buitrago-Lopez A et al.:Chocolate consumption and cardiometabolic disorders: systematic review and meta-analysis. BMJ. 2011;343:d4488.)
- ��top
���Г��ɂ̌����ƂȂ��i
- �j�g���O���Z����(�Ɏ_��)�A�J���V�E���h�R��A�y���T���`���Ȃ̂悤�ȋ��͂Ȍ��NJg���܂́A
���ǐ����ɂ��������܂��B - �~���܂̃��Z���s���́A�Z���g�j�������̂��ߌ��ǐ����ɂ�U�����܂��B
- ���ɖ�̃C���_�V���́A�A�p�ɂ��Q�T�`�T�O���ɐ₦���݂����ɂ��N����܂��B
- ��top
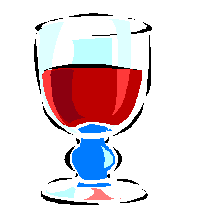 �����Ɠ���
�����Ɠ���
�������Ɠ��ɁA�Ƃ��ɂԂǂ����Ɠ��ɂ̊W
- ���[�}�鍑����ɂ́A�Ԃǂ����͕Г��ɂ̂��ƂƂ����Ă��܂����B
- �I���O�R�O�N����A�P���X�X�́u�Ԃǂ��������ނƓ��ɂ��N���襥����U�̂������肩�����ċN�������v�Ə����Ă��܂��B
- Aulus Cornelius Celsus ���v�N�s�ځB1���I������Ɋ����Ñネ�[�}�̒���ƁB�S�Ȏ��T���̒��������킵���j
- �ԂԂǂ����ɂ̓q�X�^�~�����Ƃ��ɑ����܂܂�Ă��܂��B
- �q�X�^�~���͌��ǂ��g���������ɂ��N�����܂��B
- ����ƃ`���~���̂����œ��ɂ��N����̂ł��B
- ���Ԃǂ����͂����̕��������Ȃ��̂ŁA���ɂ̌����ɂ͂Ȃ�ɂ����̂ł��B
- ���Ԃǂ����ɂ��U������铪�ɂ��Ƃ��Ɂu�V�����h�l���Ɂv�Ƃ����܂��B
- �������ɂ̓q�X�^�~�����܂܂�܂���B
- �����œ��ɂ�����̂̓A���R�[���̕����Y��(�|�_�Ȃ�)�̂����ł��B
- ���ʂ̈��������Ă���ʍg���A���ɁA�q�C������̎��̕��́A�A���R�[���̕����y�f����V�I�Ɍ��R���Ă��܂��B
- �����y�f�����ǂ͂Ƃ��ɓ��m�l�ɑ����i30�`45���j�A�����oriental flush�Ƃ����܂��B
- �Г��ɔ���̒���A���邢�͐����Ԃ͐ԂԂǂ��������ɂ�U�����܂���B
�����炭�͌��ǂ����������ɂ��邽�߂Ǝv���܂��B
���A���R�[�����̃q�X�^�~���ܗL��(�P�ʂ�mg/L)
- �J���t�H���j�A�E���C���ԁ@�@�@ 0.3 - 15.5
- �J���t�H���j�A�E���C�����@�@�@ 0.6 - 11.4
- �C�^���A�E���C���ԁ@�@�@�@�@�@ 2.5 - 2.8
- �h�C�c�E���C�����@�@�@�@�@�@�@ 0.04
- �t�����X�E���C���ԁ@�@�@�@�@�@14.6 - 15.6
- �t�����X�E���C�����@�@�@�@�@�@ 0.19
- �o�T�̓����X�u���ɂɋ����Ȃ�v
- �q�X�^�~���͂Ԃǂ����ł��u�ԁv�ɊܗL�ʂ������B�����ɂ���ĈقȂ�
- ��top
����������̓��ɂ͂Ȃ�������̂ł����B�y�ɂȂ���@�͂���܂���
- �A���R�[���͌��NJg����p������A�Г��ɂ�Q�����ɂ�U�����܂��B
- �������������y��������ł���Ƃ��ɂ͓��ɂ͂���܂���B
- ��������ɂ�铪�ɂ͕����Y��(�A�Z�g�A���f�q�h�A�|�_)�̍�p�ł��B
- �A���R�[���ɑ��ăt���b�V���O�����i��ʍg���⓪�ɂȂǁj�������l��
�A���R�[����A�Z�g�A���f�q�h���ӂ���y�f(ALDH)�̗͂��n��Ȃ̂ł��B - ���ꂾ���ł͂Ȃ���X�����A�吺�ł̉�b�A���y�A�����A�^�o�R�Ȃǂ̗v�����֗^����Ǝv���܂��B
- ��������ɂ͒��ɍ܂������܂����A���ǎ��k��p�̂���J�t�F�C���ܗL����(�R�[�q�[��Z������)�������܂��B
- �A���R�[�������̒��ł́A�ԃ��C�������ɂ�U�����₷���Ƃ����Ă���܂��B
- ����̓q�X�^�~��(���NJg����p����)���ʂɊ܂ނ��߂ł��B
- �������ɂ̓E�C�X�L�[�Ȃǂ̏������̓q�X�^�~�����܂݂܂���B
- ����ŏ������̕����o�߂��������悢�̂ł��傤�ˁB
- ��top
�����Ƀp���h�b�N�X
- �t�����X�l�͓�������i�Ȃǂ̓��������b����������ۂ��Ă���i�N�ԂP�l������̓�����ʂ̓��[���b�p�Ńg�b�v�j�ɂ�������炸�A
�������S�����ɂ�鎀�S���̓��[���b�p�ōʼn��ʁA�C�M���X�̂P�^�R�ȉ��A�h�C�c�̖�P�^�Q�ł��B - ������u�t�����`�E�p���h�b�N�X�v�Ƃ����܂��B
- �u�t�����`�E�p���h�b�N�X�v�̗L�͂Ȑ������u�ԃ��C�����v�ł��B
- �t�����X�l�̂P�l������̔N�ԃ��C������ʂ͖�U�V���b�g���Ő��E��A�C�M���X�l�̂U�D�T�{�A�h�C�c�l�̂Q�D�T�{�A���{�l�̂V�O�{�ł��B
- �����Ċe�����C������ѓ����b����ʂƋ������S�������S���Ƃ̊W�����������Ƃ���A
���C������ʂƋ������S�������S���̊Ԃɋt���ւ̂��邱�Ƃ����炩�ɂȂ�܂����iRenaud, S.��A1992�j�B - �܂��Ɂu���͕S��̒��v�̂Ƃ���ł�
- �ԃ��C�����S�O�O�`�T�O�O�~�����b�g���^���A�Q�T�Ԉ��܂����Ƃ���A
�k�c�k-�R���X�e���[��(���ʃR���X�e���[��)�̎_����R�����L�ӂɏ㏸���܂����i�q�ALancet�A1994) - �ԃ��C���̍R�_���쌾�p�́A�a�������^���j���A�Ԃ��F�f�A���g�V�A���Ȃǂ��|���t�F�m�[���ɂ����̂Ƃ���܂��B
- �|���t�F�m�[���́A�ԃ��C�����Ԃǂ��̉ʓ������łȂ��A�ʔ���Ȃǂ��ꏏ�ɂԂ��Ĕ��y�����邱�Ƃ��瑽�ʂɊ܂܂�܂��B
- �ł�����������菜���Ĕ��y�����锒���C���ł͋����R�_����p�͂���܂���B
- ���N�ɂ悢�ԃ��C�������ɂ̌����Ƃ͔���ł��B
- �����Âߓ��Ƀp���h�b�N�X�Ƃ��ł����܂��傤
- �m�Q�l�n�ߓ��a�Y�A�q�O�d�F �ԃ��C�����N�@�A�P�X�X�T�D�����[�D
- ��top
�� ���x
- �����A���R�[���Z�x(mg/dl)�ƏǏ�
- 0�`100 �y�x����--------------��ʍg���A�����A�z�C�A���فA�������̑̂̓��h�A�ċz���i�A���������A�y�x�̌����㏸
- 100�`200 �����x����----------����s����i�{��A�����A���ԁj�A���f�͒ቺ�A�^�������i�璹���j�A�L����Q
- 200�`300 ����E���x����-----�^�������������ŕ��s����A����s���āA���S�E�q�f
- 300�`400 �D����--------------�ӎ���Q�A�召�֎��ցA�����˂͏����A�ċz�͐[���ɏ�
- 400�`�@�@������---------------�����A450�ȏ�ɂȂ�ƌċz��Ⴢɂ�莀�S
- �o�T�F�琰�F�A���R�[���ɂ��O���Ƃ��̑Ή�.JIM4(7):596-598,1994�j
- ��top
���A���R�[�������Z�x�̐���
- �������҂�f�@����ꍇ�A���߂Ɋ��҂����x�A���邢�̓A���R�[���̌����Z�x�𐄒肷��B
- �M�҂炪�����Z�x�ƗՏ��Ǐ�A���Ȃ킿�A
- (1)�A���R�[���L
- (2)�����[���x
- (3)�ӎ����x��
- (4)�����^��
- (5)�Ǐ��Ǐ�i�^����ჁA�]�_�o�Ǐ�j
- (6)���ꖾ�ēx
- �Ƃ̊W�����������Ƃ���A�A���R�[�������Z�x�́A
(1)�A���R�[���L�A (2)�����[���x��2�̈��q�Ő��肵���邱�Ƃ������ꂽ�B - Y��101X1�{30X2-126
Y�F�����Z�x�img�^dl�j
X1�F�A���R�[���L�̒��x�i1�F�Ȃ��A2�F�킸���A3�F���Ȃ�A4�F�Ђǂ��j
X2�F�����[���x�i1�F�Ȃ��A2�F�y�x�A3�F����j - �o�T�F�琰�F�A���R�[���ɂ��O���Ƃ��̑Ή�.JIM4(7):596-598,1994�j
- ��top
����������Ƃ�
����`
- �A���R�[���ɂ������N�����ꂽ�}�����ł������܂őJ��������Ԃł���B
- �A���R�[�����E�nj�Q�ł�����B�E�����֗^���Ă���B
- ���Ɂ@���d�`�K���K�����d
- �����ߕq
- �߂܂��A���Ȃ�
- ���������A�m��
- bad mouth
- ���S�E�q�f
- �S�g�E�́A���ӊ�
- �E��
- �ጌ��
- �A�V�h�[�V�X
- ��J���E�����ǁA��J���V�E������
- �ݓ������@�@�ݔS���̕���A���ԁA�r�����A�o��
��������̃��J�j�Y��
- �P�D�A�Z�g�A���f�q�h
- �A���R�[���͊̑��ŕ��������B
- �E���f�y�f�ƕ⏕�y�f��NAD�i�j�R�`���A�~�h�E�A�f�j���E�W�k�N���I�`�h�j���֗^�B
- �A���R�[���˂��A�Z�g�A���f�q�h�ː|�_���˒Y�_�K�X�{��
- ���{�l�̓A���R�[�������\�͂��Ⴍ�������x���B
- �A�Z�g�A���f�q�h������������Ȃ��ƑS�g�̌����ֈ�ꂾ���B
- �A�Z�g�A���f�q�h�͋����Ő�������A������̌����ɂȂ�Ƃ����Ă���B
- �Q�D�R���W�i�[�i�������j
- ���ɂ͎��̕��������o����R���W�i�[���܂܂�Ă���B
- �i�y��c�����A�t�[�[�����A�L�@�_�A�A���f�q�h�A���ނ�F�f�j
- �����ɂ͓Ő�����������A�̉�łɕ��S��������B
- �R�D�ጌ��
- �̑�����̓��̕��o�͗}�����ꌌ���͒ቺ����B
- �S�D�E���A�d�����ُ�
- �A���R�[���͑̓��̐�����D���E����p�ƔA�̔r�������Ȃ������A��p������B
- �J���V�E���A�}�O�l�V�E���A�J���E���A�r�^�~��B1/B2/C�Ȃǂ�̓�����r�o����B
- �q�f�≺���ɂ��A�J���E���A�}�O�l�V�E����������B
- ���̌��ʁA�E�́A�����Nj@�\��Q�A�s�����̌����ƂȂ�B
- �\�h
- �A���R�[���͓ŕ��ł���ƔF�����邱�ƁB���܂Ȃ���u���S�ȑ�v�ɂȂ�B
- �R���W�i�[�̏��Ȃ������ȃA���R�[���ɋ߂����̂ɂ���i���������悢�j�B
- �A���R�[���Z�x�̍������̂ƒႢ���̂͋z���Ɏ��Ԃ������邱�Ƃ�m��B
- �̑��ŃA���R�[�����X���[�Y�ɑ�ӂ����悤�ɂ��������ށB
- �z���x�点��ɂ͖����ɕx�H�ו��͗L���ňݔS���̕ی�ɂ��Ȃ�B
- �Y���������݂���̋z����x�点��B
- �܂��r�^�~��A/B1/B2/C�͈��ޑO���⋋���Ă���
- �L���x�c�A�r�^�~��C�̓A���f�q�h���z������B
- �L���[�g���܂ŐH���@�ۂ𑽂��܂ނ���ɂႭ�A�C�����悢�B
- ��
- �P�D�f��
- �݉�������ΐ����t���Ȃ��łЂ�����f�������Ȃ��B
- ����Ȏ��ɂ͐Â��ȈÂ������Œg��������B
- �����Ɖ䖝���ăA���f�q�h�̕�����҂B
- �݉��ł���Έ݂���ɂȂ�ς�����x���������B
- ���₯�ɂ͈ݖ�i���_�܁j�Ŋɘa�ł���B
- �����͈ݔS����핢����̂œf���̍ۂɂ����߂���B
- �Q�D���C��V�����[
- ���ނƐ������[���ɕ⋋���Ă������ق������S�ł���B
- �ʂ邢���C�����߂�B�M�����͗L�Q
- �T�E�i�͊��߂��Ȃ��B
- �P�D�f��
- �R�D�������d�����⋋
- �~�l��������̃h�����N�܁A�J���E���𑽗ʂɊ܂ރI�����W��g�}�g�̃W���[�X��
- �g�����X�[�v�ށA��
- ���ނ͉ʓ����悢�B�I����ʕ��Ƃ��ɂԂǂ����悢�B
- �������̃K�u���݂Ɨ₽�����鐅�͈݂��h������B
- �r�^�~��A/B1/B2/C�̕⋋
- �S�D����
- ���ɖ�̓A���R�[���݉�������������B
- �J�t�F�C���i�R�[�q�[�E�Β��j�͓��ɂ��y�������邪�A�݂̏�ԂƑ��k����B
- ��p�Y�̓A���f�q�h���z������B
- �T�D�}����
- �A���R�[�����E�nj�Q�ɂ͂���Ȃ�ɗL���ł��邪�E�E�E�E
- �����������r�[���i�C�̔��������́j���ǂ��i�t�F���l�u�����J�Ȃǃr�^�[�X�����炷�j
- �L���̂Ȃ��E�I�b�J�x�[�X�̃J�N�e�����g����B
- �U�D�a��@��f
- �d�ǁA������]�̏ꍇ�͎�f
- �_�H
- �_�f�z��
- �o�T�FDr.�؏Z��́wWeb�̈�w�x�@��������u�� �@http://www.j-mac.co.jp/medi/drunk/
- ��top
- �ł���������Ɍ������Õ��@
- �����...�R�[�q�[�ƃA�X�s�����ł��B
- �A�����J��Michael Oshinsky���m��͓���������b�g��p���������ŁA
����������ɂ̌����̓A���R�[��(�G�^�m�[��)�̑�ӕ��̃A�Z�g�A���f�q�h�ł͂Ȃ��A
���ꂪ����ɕ������ꂽ�u�A�Z�e�[�g�i�|�_�j�v���ł��邱�Ƃ�˂��~�߂܂����B - �J�t�F�C���Ə������ɖ������́u�A�Z�e�[�g�v��h���A���ɂ������邻���ł��B
- ��̓I�ɂ̓o�t�@�����ƃR�[�q�[�œ��������������Ă��Ƃł��B
- ���� Maxwell CR, Spangenberg RJ, Hoek JB, Silberstein SD, Oshinsky ML. Acetate
causes alcohol hangover headache in rats. PLoS One. 2010;5(12):e15963.
http://www.gizmodo.jp/2013/06/post_12637.html - ��top
�����̈��߂�l�A�t���Ȃ��l�̍�
- �����ɂ�铪�ɂ̌��������̓A�Z�g�A���f�q�h���B����͎�Ɋ̑��ő�ӂ����
- �A���R�[���˃A�Z�g�A���f�q�h�ː|�_�ː��Ɠ�_���Y�f�ɕ��������
- ALDH2�̓A�Z�g�A���f�q�h������̂ɏd�v�ȍy�f�ł���
- ALDH2�������`�q�̌^�̈Ⴂ�ɂ����ɋ����A�ア���ł���
- ���̈�`�q�ɂ́A����\�͂̋���N�^�Ɠ����̎アD�^��2��ނ�����
- ���e�������p����`�q���Ƃ���N�^(NN)�Ȃ�u���߂�̎��v
- �j����1���ԂŖ�10�O���������ł���B�r�[�����r����
- N��D�̗������p���ł���Ɓu���܂���߂Ȃ��^�v
- �Ƃ���D�^(DD)���Ɓu�S�����߂Ȃ��̎��v
- �����̋����肷��p�b�`�e�X�g�ɂ��Ă�http://www.a-h-c.jp/bookstaihan.html
- 2002�N(����14�N)12��23���@�����V�����
- ��top
- ���������߂Ȃ��l���P���ň��߂�悤�ɂȂ���Ė{���H�������݂͖����������Ȃ��Ȃ���Ė{���H
- �~�g�R���h���A�ɂ̓A���R�[���̕����ߒ��Ŕ�������A���f�q�h�ނ�����ALDH�Ƃ����y�f������܂��B
- ���̍y�f����V�I�������Ă���ƃA���R�[�����t���Ȃ��Ȃ�܂��B
- ���������߂Ȃ��ЂƂ����߂�悤�ɂȂ�̂�ALDH�Ƃ͕ʂ�ME0S(�~�N���]�|���G�^�m�|���_���y�f)�Ƃ����y�f���͂��炭�悤�ɂȂ邩��ł��B
- ������ME0S�̓A���f�q�h�ނ�����Ƃ��Ɋ����_�f�������Ă��܂����ƁA
������͖���ٕ��ƔF�����ĕ������Ă��܂�����
���̌��ʖ����������Ȃ��Ȃ�Ȃǂ̕s�s��������܂��B
�o�T:�m�g�j�T�C�G���X�y�d�q�n�@�~�g�R���h���A�̐V�펯 (NHK�T�C�G���XZERO)2011�N - ��top
�A���R�[���̓K��
- ���J�Ȃ͐ߓx����ʂƂ���1����20�O������E�߂�B
- �A���R�[�����N��w����ihttp://www.arukenkyo.or.jp�j��
���{���P���Ɋ܂܂��A���R�[��22�O����1�P�ʂƂ��āA2�P�ʂ܂ł����e�B - 2�P�ʂ́A�r�[����r2�{�A�E�C�X�L��_�u��2�t�B
- ����̎������X�ƈ��ނƁA�������肪�ς���Ĉ��݉߂��ɂȂ�₷���B
- �ڂ����m�肽���l�̓I�[���A�o�E�g�W���p���́u�ƒ�̈�w�v
http://allabout.co.jp/health/familymedicine/closeup/CU20021118M/�j
�́A��ʂƐ��������߂�܂ł̎��{�̊W����̓I�ɐ����B - �A�T�q�r�[����http://www.asahibeer.co.jp/8_19htm/gbook.htm
���Q�l�ɂȂ�B - (�����V��2003.7.7)
- ��top
��������̂Ƃ��̂Ɠ���
- �y2005���ۓ��Ɋw��z �ӂ�����ރA���R�[���ʂ������Ɠ�������̂Ƃ����ɂ͋N����ɂ���
- Yokoyama Y et al. Hangover headache in Japanese male workers. Cephalalgia,2005; 25:988
- ��top
��������ɏ��m�b�@�v���l�A���R�[���ǃZ���^�[���@���ɕ���
- ������̃A�Z�g�A���f�q�h�̌����Z�x�̌�������u�A�Z�g�A���f�q�h����������̌����Ƃ͍l���ɂ����v�B
- ��������̌����́u�ʂɂ���v�B
- ��������̌����͎l��
- ���A���R�[�����c������
- ���ጌ�����
- ����J
- ���A���R�[���̗��E�Ǐ�B
- ���������h���ɂ�
- ����ʂ�}����
- ���H�ׂȂ������
- ���A���R�[���̕����𑬂߂�ʓ����܂܂��ʕ���H�ׂ�
- �o�T�@�����V���@2008�N4��25���@��������
- ��top
���K�������̂P�O�J���@�i�A���R�[�����N��w����쐬�j
- �q�P�r���Ȃ���A�Ƃ��Ɋy����������
- �q�Q�r�����̃y�[�X�ł�������
- �q�R�r�H�ׂȂ�����ޏK����
- �q�S�r�����̓K�ʂɂƂǂ߂悤
- �q�T�r�T�ɂQ���͋x�̓���
- �q�U�r�l�Ɏ��̖��������͂��Ȃ�
- �q�V�r������ƈꏏ�ɂ͈��܂Ȃ�
- �q�W�r�����A���R�[�������͔��߂�
- �q�X�r�x���Ă���P�Q���Ő�グ�悤
- �q10�r�̑��Ȃǂ̒��������
- �i�߂��A�D�Y�w�ƌ������^����̈����֎~���Ăъ|������e�����荞�ށj
- �����V���@2008�N4��25���@��������
- ��top
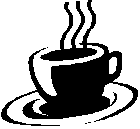 �R�[�q�[�Ɠ���
�R�[�q�[�Ɠ���
���J�t�F�C���͕Г��ɂɂ悢
- �J�t�F�C���͖��C�E��J�����Ƃ�A�v�l�͂⒍�ӗ͂������܂��B
- 17���I�A�X�C�X��Samuel Andre Tissot�͐_�o�w�̋��ȏ��ŃR�[�q�[��Г��ɂ̎��Ö�Ƃ��đE�߂Ă��܂��B
- �Г��Ɋ��҂��Z���R�\�q�\���ނƓ��ɂ�����o�������܂��B
- �J�t�F�C���́A�R�[�q�[�Ƃ����ɂƂ���1�J�b�v������50�`150mg���ӂ��܂�Ă��܂��B
- �s�̒��ɖ���h�����N�܂Ȃǂɂ��܂܂�Ă��܂��B
- �u�Г��ɂ��h�����N�܂����ނƊy�ɂȂ�v�Ƃ����������܂������A����̓J�t�F�C���̂����ł��B
- �Г��Ɏ��Ö�ɂ̓J�t�F�C�����z�Ⴓ��Ă��܂��B
- �J�t�F�C���̓G���S�^�~���̌��ʂ����܂��B
- �J�t�F�C���̓G���S�^�~���̋z���𑣐i���܂��B
- �J�t�F�C���͔]���ǂ����k�����܂��B
- ���L�̌����ɂ��J�t�F�C�����̂����͂ȕГ��Ɏ��Ì��ʂ�����Ƃ������Ƃł��B
- Ward N et al: The Analagesic Effects of Caffeine in Headache. Pain 44:151-155, 1991
A direct analgesic effect of caffeine in patients with nonmigrainous headaches.
affeine acts by stimulating D2 or alpha-2 receptors in the CNS. - �J�t�F�C���ْ͋��^���ɂɂ��悢�悤�ł��B
Diamond S, Balm TK, Freitag FG: Ibuprofen plus caffeine in the treatment of tension-type headache. Clin Pharmacol Ther 2000, 68: 312-319 - ��top
���J�t�F�C���֒f���ɂ̍��ۓ��Ɋw���`
�V�(ICHD-�U) 8.4.1 �J�t�F�C�����E���Ɂ@�f�f��F
- A. C�����D���������� ����сE�܂��� �������̓���
- B. 2�T�Ԃ��āA1��200mg�ȏ�̃J�t�F�C���ێ悪����A���ꂪ���f�܂��͒x�����ꂽ����
- C. ���ɂ͍Ō�̃J�t�F�C���ێ��A24���Ԉȓ��ɔ������A100mg�̃J�t�F�C���ɂ��1���Ԉȓ��Ɍy������
- D. ���ɂ̓J�t�F�C���̊��S���E��A7���ȓ��ɏ�������
- ���
- A. ����15���ȏ�i500����/���j
- B. �Ō�̃R�[�q�[���p����24���Ԉȓ��ɋN����
- C. 100�����̃J�t�F�C���ɂ��ɂ����܂�
- ��top
���J�t�F�C���ˑ�������
- �J�t�F�C���͉�M���ɍ܁A�������`��A���P��႖�A�@���p������A��蕨�����\�h��A���ɍ܁A
������A�h�����N�܁A�R�[�q�[�E���Ɋ܂܂�Ă��܂��B - �J�̓J�t�F�C�����炯�ł��B
- �J�t�F�C���ɐ��_�ˑ���������܂��B
- �m�炸�m�炸�̂����ɃJ�t�F�C������肷���Ă��܂��܂��B
- �Ⴆ�A�R�[�q�[������R�t�A�h�����N�܂��Q�{�A���ɖ���̂ނ�
���500mg�̃J�t�F�C�����Ƃ邱�ƂɂȂ�܂��B - �����Ĉ��500mg���̂悤�ɐۂ�ƃJ�t�F�C���֒f���ɂ��N����܂�(�V��ł�1��200mg�ȏ�)�B
- ������J�t�F�C���̐ۂ�߂��ɐS��z�肽�����̂ł��B
- �����Ăǂ̈����ɂǂ̒��x�̃J�t�F�C���������Ă��邩�m���Ă����������̂ł��B
- ��top
���J�̓J�t�F�C�����炯�ł�
- �ꌎ��15���ȏ�i500����/���j�ŋ֒f�����ɔ������܂�
- �J�t�F�C���ܗL�ʂ̖ڈ�
- �h�����N�܁@�@50mg
- ���ɖ�@�@�@�@50mg���x
- �R�[���P�t�@�@50mg
- �R�[�q�[�P�t�@100�`150mg
- �����P�t�@�@�@50�`75 mg
- �����m��Ȃ��ԂɃJ�t�F�C������肷���Ă��܂�
- ���̂悤�ȕ��͍Ō�̃J�t�F�C���ێ悩��24���Ԉȓ��ɓ��ɂ��N����܂�
- �J�t�F�C���֒f���ɂ̓J�t�F�C���Ŏ���̂������ł�
- �ł�����܂��܂��݂̂����Ă��܂��܂�
- �v����������͒��ӂ��Ă�������
- �����F�����A��N�҂̃R�[���̐ۂ�߂�����J�t�F�C���U�����ɂ��N����
- ����Headache World 2000, London, UK 3-7 Sept 2000 no.50
- ��top
���J�t�F�C���֒f������
- �J�t�F�C���g�p���~�͔������ۂƂ��Č��NJg���������ē��ɂ������N�����܂�
- �J�t�F�C��������Ă���ƈꎞ�Ԍ�ɔ]���[�����A���̂̂��ɓ��ɂƂȂ�܂�
- ���ꂩ��R�`�U���Ԍ�Ƀs�[�N�ƂȂ�܂�
- ���ɂ͍ŏ��A�㓪�����邢�͒��S���Ɏn�܂�A�S�ʉ����Ă����܂�
- ���ɂƂƂ��ɖ��C�A��J��������܂�
- �^���ň������܂�
- ���Ɉ��S�E�q�f���Ƃ��Ȃ��܂�
- �u�ޖ̓��Ɂv�������l�̐ێ�ʂP������616 mg�ł��i�l����j
- �J�t�F�C���̕���p�i�}���Ǐ�j
- �P��250 mg���� �_�o�ߕq�A�����A������Q�A��ʍg���A���A����ш��S�A�q�f�Ȃǂ̈ݒ��Ǐ�
- �P��1000 mg���� �ؓ��̕s���ӂ̂��k�A�s�����A���_�������g�A����
- ����ȏ�i�J�t�F�C���ǁj�@ ����A�M���Ȃǂ̊��o��Q
- �Q�l�}���F�u�ˑ��v�@�x���������@��g�V��
- ��top
- Cephalalgia 2004;24(4):241 Caffeine-withdrawal headache. The Vaga study of headache epidemiology
O Sjaastad, Ls Bakketeig
�˃J�t�F�C�����E���ɂɂ��Ă�Vaga study�B
1���ɂ�����4.7�t�B���E���ɂ̕p�x��0.4%�B�R��)10�t/���in =31�j�͏T���̊ԁA�J�t�F�C�����E���ɗl���ɂ��N�������B
��ʑ�O�̃��x���̃J�t�F�C��-���E�����ɂ́A�ނ��뒿�����A��ʂɔ��R�Ƃ����A�Ǐ�̏��Ȃ����ɂł���\��������B - ��top
���e������A��܂̃J�t�F�C���ܗL��
�h�����N�܂̃J�t�F�C����
- ���i��/�K�i/������/�J�t�F�C��/�A���R�[��
- ���{�r�^��D/100ml/�吳����/50mg/�|
- ���{�r�^���S�[���h/50ml/�吳����/40mg/��
- ���{�r�^��D�X�[�p�[/100ml/�吳����/50mg/�|
- ���{�r�^��A/50ml/�吳����/�|/��
- �A���i�~����/50ml/���c��i/50mg/�|
- ���Q�C��/50ml/�O��/50mg/��
- �V�O�������g/100ml/���O����/30mg/�|
- �O�����T��DX/50ml/���O����/50mg/��
- �O�����T�������t/20ml/���O����/50mg/�|
- �`�I�r�^�h�����N/100ml/��Q��i/50mg/�|
- �v���Z���g�b�v�t/30ml/�G�X�G�X/50mg/�|
- ���[�����O�����r�^�[�����t/30ml/��Ֆ�i/40mg/��
- �r�^�V�[�X�[�p�[�S�[���h/50ml/��Ֆ�i/50mg/�|
- �����P��D/50ml/��������/50mg/�|
- �����P������t/30ml/��������/50mg/��
- �o�T�F���N�X�|�[�c�h�N�^�[�ւ̓��i��R���j ����4�D�s�̃h�����N�܂̃J�t�F�C���ܗL��
- ��top
�e�풃�ނ̃J�t�F�C���ܗL�ʁi�Z�o�t�j
- �J�t�F�C��(%)
- �ʘI 0.16
- ���� 0.02
- �Ԓ� 0.01
- �ق����� 0.02
- ���Ē� 0.01
- �E�[������ 0.02
- �g�� 0.05
- ���M�����[�E�R�[�q�[ 0.04
- ���\�����u���E�R�[�q�[ 0.05
- �����F�l���H�i�����\�y�с��̓l�X�����{�i���j���ׁB
- ��top
���ɖ�̃J�t�F�C���ܗ�
- �o�t�@����A���i���C�I���j�@�@�Ȃ�
- �i�����G�[�X���i�吳�j�@2�����@50mg
- �m�[�V�����i�A���N�X�j�@2�����@70mg
- �C�vA�� �i�G�X�G�X�j�@�@2�����@80mg
- �V�Z�f�X���i�V�I�m�M�j�@1�����@40mg
- �i�������i�吳�j�@�@�@�@2�����@50mg
- �n�b�L���G�[�X�����i���сj3��@225mg
- �Z�f�X�n�C ���i�V�I�m�M�j�P����25mg
- �P�������U�i���O��i�j1��@ 60mg
- �����p�o�t�@����C�U�� �i���C�I���j�Ȃ�
- �J�t�F���S�b�g�@�����J�t�F�C��100����
- ��top
���J�t�F�C���֘A��Q�@Caffeine-related Disorders
- DSM-IV ���_�����̕��ނƐf�f�̎�����@��w���@�ɂ��ƃJ�t�F�C���U������Q
�Ƃ��ĉ��L�̂S��ނ��������Ă��܂��B - 305.90�@�J�t�F�C�����Łi��͉��L���Q�Ɓj
- 292.89�@�J�t�F�C���U�����s���Ꮡ
- 292.89�@�J�t�F�C���U����������Q
- 289.9 �@����s�\�̃J�t�F�C���֘A��Q
- 305.90�@�J�t�F�C������Caffeine Intoxication�̒�`�͈ȉ��̂Ƃ���ł��B
- A �J�t�F�C���̍ŋ߂̏���Œʏ�250mg���z������́i��F���������R�[�q�[2�A3�t�ȏ�j
- B �J�t�F�C���̎g�p���܂��͎g�p��܂��Ȃ���������ȉ��̒���̂���5���ځi�܂��͂���ȏ�j�D
- �i1�j�������̂Ȃ�
- �i2�j�_�o�ߕq
- �i3�j����
- �i4�j�s��
- �i5�j��ʍg��
- �i6�j���A
- �i7�j�ݒ��n�̏�Q
- �i8�j���k
- �i9�j�U���Ȏv�l����щ�b
- �i10�j�p���܂��͐S���s��
- �i11�j���m�炸�̎���
- �i12�j���_�^������
- D �Ǐ�͈�ʐg�̎����ɂ����̂ł͂Ȃ��A���̐��_�����i��F�s����Q�j�ł͂��܂���������Ȃ�
- ��top
���J�t�F�C���̍�p�@��
- �Β���R�[�q�[�ȂǂɊ܂܂��A���J���C�h�ŁA�L�T���`���U���̂ƌĂ��B
- �J�t�F�C���̓h�[�p�~���𐧌䂵�Ă���w�A�f�m�V���x�ƍ\�������Ă���
- �J�t�F�C���̓A�f�m�V����e�̂Ɍ�������
- ���̂��߂Ƀh�[�p�~���𐧌�o���Ȃ��Ȃ�
- ���̌��ʁA�h�[�p�~���̋�����p�������Ȃ�
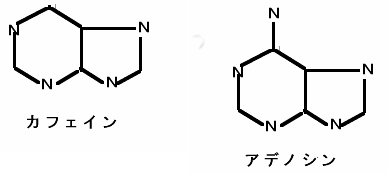
- ��top
���R�[�q�[�̂����v
- �s�����ۂ����炷�B�ݒ�ᇁA�݂�������炷�B
- ���C�������A�W���͂����܂�
- ����������}����
- �����_�f����������
- �o�T(�����V���@2001.10.22)
- ��top
- �J�t�F�C���͍���҂̋L���͂����߂�@�o�T�FCaffeine boosts memory in older adults�@(Psychol Sci 2002;13.)
- ��top
- �R�[�q�[�ێ�ƃp�[�L���\���a�͔����̊W (Benedetti MD, et al. Neurology 55:1350 2000.)
- ��top
- 2003.2.26�@�u�R�[�q�[�����҂͓��{�l�ł����A�a�����Ȃ��v
�P���V�t�ȏ�R�[�q�[�����ސl�́A�P���Q�t�ȉ��̐l�����A�Q�^���A�a���Ǘ����T�����Ȃ�(�̃I�����_�̌����ALancet��11���X�����Ɍf��)�A�����J���ȑ��ړI�R�z�[�g�����ł��R�[�q�[���T�P��ȏ���ސl�ɂ́A�������������P�[�X�����Ȃ��Ƃ���(MediPro�f�ڋL��)�B - ��top
- �R�[�q�[�ێ�Œ_�̔����������@��w�̂���� 2004;208(9):776
- ��top
- �ŋ߂̌����ł͓���I�ȃR�[�q�[�̈��p�œ��A�a��p�[�L���\���a�Ƃ��������������̃��X�N���������Ȃ�\�����w�E����Ă��邪�A����I�ȃR�[�q�[�̈��p�Ŋ̊��ƌ��������\�h�ł���\��������Ƃ������������\���ꂽ�B���{�̌����҂ɂ��A����I�ɃR�[�q�[�����ސl�̊̊��̔��������A�܂��������܂Ȃ��l�̂��悻�����ł��邱�Ƃ��������B�܂��A�n�[�o�[�h��w���O�q���w���̌����ɂ��A�J�t�F�C�������̃R�[�q�[�������������ɑ��ĕς��Ȃ����ʂ�����B�����������͂قږ����R�[�q�[�����ސl�̊̊����X�N�́A�R�[�q�[���܂��������܂Ȃ��l�̂��悻�����ł���Ƃ����B
Michels, K. and Inoue et al. Journal of the National Cancer Institute, Feb.16, 2005; vol 97: pp 282-292 and 293-300.
WebMD Medical News: "Coffee: The New Health Food?" - ��top
- �R�[�q�[�Œɕ��̃��X�N���ቺ
�R�[�q�[�𑽈�����j���͒ɕ��ɂȂ�ɂ����B
1��4�t�ȏ�Œɕ��̃��X�N��40%�ቺ���邱�Ƃ��J�i�_�^�č��̌����Ŏ�����Ă���B
�R�[�q�[�͋��͂ȍR�_�������ł���t�F�m�[���N�����Q���_�̎�ȋ������ł���A���ꂪ�ɕ����X�N�ɉe�����y�ڂ��Ă���B
�o�T�F����Ãj���[�Xm3.com 2007�N5��31�� - ��top
- ���R�[�q�[�ƍg�����]����(�]�[��)��\�h����\��������
- ����13.6�N�Ԃ̒ǐՊ��Ԃɂ������K�̓v���X�y�N�e�B�u�i�O�����j�ώ@�����ɂ��A
1���ɃR�[�q�[��8�t�ȏ���ގ҂́A���܂Ȃ��l�ɔ�ׂĔ]�[�ǂ̃��X�N��23%�Ⴍ�Ȃ�A
�g����1����2�t�ȏ���ގ҂́A21%�Ⴍ�Ȃ����B
���R�́u�R�[�q�[��g���̓t�F�m�[�����������܂݁A���ꂪ�R�_����p�������Ă��ăA�e���[���������d����\�h���邩��v�B
���́̕wStroke.2008;39:1681-1687.�x�Ɍf�ڂ���Ă���B
�R�[�q�[���g���́A��������R�_�������ł���B
�R�[�q�[�͉��ǂ���ѓ���@�\��Q�ɑ��Ă悢�A�ւ�����A�C���X�����������P���ĂQ�^���A�a�̃��X�N�����炷�B
�|���t�F�m�[���ނ��܂ލg�������l�ł���A�R���X�e���[���̎_����h�~���A�����������ƁA���ǂ̃}�[�J�[�ł���CRP��������B
2008�N07��10�� - ��top
- �� �R�[�q�[�A�q�{�̂���\�h�@�����R�t�Ŋ댯�x�U����
�����ʐM�Ёy2008�N9��1���z
�u�w�������ʂ��A�����J���Ȍ����ǂ����\�����B - ��top
- �R�[�q�[�̐ێ�ɂ��]�����̃��X�N���ቺ����\��������ƁA�X�E�F�[�f���̃O���[�v��Stroke 2011; 42:908-912.�ɔ��\�����B
����3��4�A670���O�����ɒǐՂ��A�R�[�q�[�ێ�Ɣ]�������ǂƂ̊W�����������B
����10.4�N�̒ǐՂ�1,680��ɔ]�����̔��ǂ��m�F���ꂽ�i�]�[��1�A310��A�]�o��154��A���������o��79��A�s��137��j�B�R�[�q�[�̐ێ�͔]�����S�́A�]�[�ǂ���т��������o���̗L�ӂȃ��X�N�ቺ�ƊW���Ă����B�]�o���ɂ��Ă͗L�ӂȃ��X�N�ቺ�͌����Ȃ������B
1���̃R�[�q�[�ێ�1�t�������Q�Ɓi1.00�j�Ƃ����]�����S�̂̑����X�N��1�`2�t��0.78�A3�`4�t��0.75�A5�t�ȏオ0.77�������iP��0.02�j�B - ��top
���J�t�F�C���̐ۂ�߂������ɁE�߂܂��̌�����-�ۂ�߂��ɋC��t���܂��傤
- ���ɍ܁A������A�h�����N�܂ɂ͂P���i�{�j�������50mg�A
�R�[�q�[�E���ɂ�100mg�O��̃J�t�F�C�����܂܂�Ă��܂��B - 250mg/���Ƃ�Ƌ����Ǐ��炩�ƂȂ�܂��B
- ���500mg�̃J�t�F�C�����Ƃ�Ƌ֒f�Ǐ�Ƃ��ē��ɂ�����܂��B
- �J�t�F�C���͂Ђ��떳�ӎ��ɐێ悵�Ă��܂��B
- ���ɂ����̕��̓J�t�F�C���̐ێ�ʂɂ��C��z��܂��傤�B
���R�[�q�[�̈��݉߂����߂܂��̌�����
- �e���r�ԑg�����Ђ�20��̏����͒��ߐ�ԋ߂ɂȂ�ƘA���R�[�q�[5�A6�t�ƃh�����N��2�A3�{������ł����B
- �J�t�F�C�����T����悤�w���������ʁA�߂܂��͌y�������B
- �P���ɂƂ郂��600�~���O�����ȏ�ɂȂ�ƁA�C���C����s���Ȃǂ̏Ǐo��Ƃ����B
- �ڈ��́A
- �R�\�q�[�P�t�@�@70�`150�~���O����
- ���@�@�P�t�@�@50�`100�~���O����
- �g���@�@�P�t�@�@30�` 50�~���O����
- �h�����N�܂P�{�@50�`100�~���O����
- �Z���R�[�q�[�Q�t�A�g���R�t�A�h�����N�܂P�{���P���Ɉ��ނƁA600�~���O��������v�Z���B
- �����Έ䕔���́u�����炭�J�t�F�C�����̂��̂Ƃ������A�J�t�F�C���ɗ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��X�g���X�̑����������������B�S�J����̂���l�͐������������Ă��������v�Ƙb���Ă���B
- �߂܂��ɂ��ẮA2001.2.4�@�����V�����j�ł̋L�����
- ��top
�J�t�F�C�������ɂɂ悢�Ƃ킩�����̂͂����납��
- 17���I���ɂ̓X�C�X�̃e�B�\�b�gSamuel Andre Tissot��
�_�o�w�̋��ȏ��̒��ŃR�[�q�[��Г��ɂ̎��Ö�Ƃ��đE�߂Ă��܂��B
�i�Г��ɃG�b�Z���X���j - �E�C���XThomas Willis�Ƃ����搶��1873�N�ɗՏ��_�o�w�̍ŏ��̋��ȏ��������܂����B
��z�����ώ@��ƋL�q�������炵���{�ł��B���̖{�ɂ͌Q�����ɂ炵�����ɂ��L�ڂ���Ă��܂��B
�Г��ɂ̗\���Ƃ��Ă̋A�O����������Ă��܂��B���ǐ��i���k���Ŋg���j�Ɍ��y���Ă܂��B
���Ö@�Ƃ��ăi�c�V���M�N�A�����āA�R�[�q�[�i17���I�̒�����ɃI�b�N�X�t�H�[�h�ɓ`������j���Љ�Ă��܂��iIsler�j - 1889�N�ɂ̓K���[�X Gowers ���J�t�F�C���L���Ə����Ă��܂��B
- ��top
PPA (���_�t�F�j���v���p�m�[���A�~��)�ܗL��ʗp���i�ƃJ�t�F�C��
- �����_�o��p��F���_�t�F�j���v���p�m�[���A�~�� (PPA)�́A�@���E������Ɋ܂܂�Ă��܂��B
- �J�t�F�C���̑�ӂ�j�Q���܂��B
- ���p�ɂ��J�t�F�C���̌��ʂ����������������Ő����܂��\��������܂��B
- (�Q�l)�����Ȉ����S�Ǖ���http://www.mhw.go.jp/houdou/1211/h1120-1_15.html
- ���J�j�Y���́A�]�A�f�m�V����e�̝̂h�R�ɂ��(�����N)
- ��top
���J�t�F�C���W����
- �D�P���̃J�t�F�C���ێ悪�َ��̐����Ɉ��e���̉\��
���X�^�[��w�i���X�^�[�j��Justin Konje���m�炪�s���������ɂ��ƁA�D�P���̃J�t�F�C���ێ�͔D�P���Ԃɂ�����炸�A�َ������}���i��o���̏d�j���X�N�Ƒ��ւ��Ă���\��������B
����̌����́A�R�[�q�[�����łȂ����ށA�R�[���A�`���R���[�g�A�R�R�A�ƈꕔ�̏�����ȂǁA�ǂ̂悤�ȃ^�C�v�̃J�t�F�C���ł��p�ʈˑ��I�ɁA�َ��̔���x���Ɋ֘A���Ă��邱�Ƃ��������B
�ڍׂ͎G��BMJ�i2008;337: a2332�j�ɔ��\���ꂽ�B - �J�t�F�C���̋��Z�\�͌����p�̓v���Z�{���ʁH�i2008/7/28�j
�k���I�����s�b�N�ł��C�I��̃h�[�s���O�^�f�Ȃǂ����Ԃ��ɂ��킹��ł��낤�B
7��28���t��BMJ Clinical Evidence �v���X�����[�X�ł́C�J�t�F�C���̋��Z�\�͌����p�Ɋւ���b�肪���グ��ꂽ�B
�J�t�F�C���̋��Z�\�͌����p�̓v���Z�{���ʂƂ������Ƃł���B�R�[�q�[�}�ɂ͘N��ł��ˁB - �������R�[�q�[�h�̂��X�N�ቺ
�X���i���������j���R�[�q�[���P���P�`�Q�t�ȏ���ޒj���́A�X������ɂ����郊�X�N���A�قƂ�Lj��܂Ȃ��O���[�v���Ⴉ�����B
�������R�[�q�[���P���ɂR�t�ȏ���ޏ����́A�قƂ�Lj��܂Ȃ��l�ɔ�ׁA��������ɂ����郊�X�N�����ɉ�����B
�̑����R�[�q�[���P���ɂT�t�ȏ���ސl�́A�قƂ�Lj��܂Ȃ��l�ɔ�ׁA�̑�����̔��a������S���̂P�ɒቺ����B
(�o�T�F���{�o�ϐV�� - 2007�N10��22��) - �R�[�q�[�h���X���Ȃ��@�P���R�t�ȏ�̒j��
�R�[�q�[��1����3�t�ȏ���ޒj���́A�قƂ�Lj��܂Ȃ��j���ɔ�ׁA�X���i���������j����ɂȂ�댯�x���Ⴂ�Ƃ̉u�w�������ʂ��A
���J�Ȍ����ǒË�����Y�搶���܂Ƃ߁A���{���w���2007�N10���ɔ��\�����B�y2007�N10��9���F�����ʐM�Ёz - �R�[�q�[�̐ێ悪�̍זE���iHCC�j�̃��X�N�ቺ�������炷
�C�^���A�̃O���[�v�ɂ��Hepatology�� 8 �����ɔ��\���ꂽ�B(2007-08-31) - �J�t�F�C�����܂ޒ��ɖ�́A�ˑ�����p���ɂ̔������i�߂邩�H������NO
Feinstein AR, Heinemann LA, Dalessio D, et al.: Do caffeine-containing analgesics promote dependence? A review and evaluation. Clin Pharmacol Ther 2000, 68:457-467. - ��2002.11.11�@�R�[�q�[�����҂͓��A�a�ɂȂ�ɂ���
http://medwave2.nikkeibp.co.jp/wcs/leaf?CID=onair/medwave/a030/216138 - 2003.2.28�@��͂�T����ׂ��A�D�P���̃R�[�q�[
�D�P���ɃR�[�q�[���P���W�t�ȏ������ł����D�w�ł́A�S������ł��Ȃ������l�Ɣ�ׁA���Y�̃��X�N���Q�{�ȏ�ɂ��Ȃ邱�Ƃ��A���悻�P��8000�l�̔D�w��ΏۂƂ����f���}�[�N�̒����Ŗ��炩�ɂȂ����B
�������ʂ́ABritish Medical Journal�iBMJ�j��2003�N�Q��22�����Ɍf�ځB - �R�[�q�[�̈����Ƃ͈��܂Ȃ��l�ɔ���������̐l���L�ӂɏ��Ȃ�
���ړI�R�z�[�g�����̌��ʁB
�R�[�q�[���T��1��ȏ���ސl�̕����A���܂Ȃ��l�������������̔䗦���L�ӂɏ��Ȃ�����(�I�b�Y��0.614�Ap<0.001)�B����A�Β��A�g���A�E�[�������̐ێ�Ƃ̑��ւ͖��������B�ێ�J�t�F�C���ʂ̐��肩��A1��������̃J�t�F�C���ێ�ʂ�100mg���������ꍇ�A���������̏o���p�x�͗L�ӂɒቺ�����B�ێ�J�t�F�C���ʂł͂Ȃ��A�R�[�q�[�����ނ��Ǝ��̂��A���������̗}���ƊW���Ă���悤���B
(Nikkei Medical 2003;3:34) - R Hering-Hanit, N Gadoth: Caffeine-induced headache in children and adolescents,
Cephalalgia 2003;23(5):332
�ˁ��J�t�F�C���U��������(�����A�v�t��)�Ƃ��ɃR�[���̈��݂����B�����A�������ɂ̌����ƂȂ�B
��N�҂̓J�t�F�C���̐ۂ�߂��Ŗ����A�������ɂɂȂ��Ă���
�T�N�ȏ�A�R�[���މ߈����̖����A�������Ɏ�N�ҁi6-18�j�@36�� (f:m = 17 : 19 )
�T�^��@�X�@
�����A�������Ɂ@1.8�N
1.5 L/�� ( 193 mg caffeine)
11 L/�T �i1415 mg caffeine�j
�R�[�������X�Ɍ��炷���Ƃɂ�蓪�Ɋ��� - ��2003.9.25�@�R�[�q�[���^�����̋ؓ��ɂ�h���|�|�Č��� the Journal of Pain��2003�N�W�����Ɍf�ڂ��ꂽ�B
- ��2003.9.25�@�R�[�q�[�ɒ_�Η\�h���ʁ@�����V��2003.9.25�@�@�j���ł͖��Ɍ������B
- ���R�[�q�[�ێ�͂Q�^���A�a���ǂ����Ȃ��B��w�̂���� 207:268, 2003
- �R�[�q�[�̖ڊo�߂��� �L���F�����ʐM�� �y2005�N6��20���z
�R�[�q�[��g���Ɋ܂܂��J�t�F�C���́A�]�̍זE����ɃA�f�m�V���`�Q�`��e�̃^���p�N���ƌ��ѕt���Ėڊo�ߍ�p���N�������Ƃ��A���o�C�I�T�C�G���X�������̗��o�ǔ��i����ŁE�悵�Ђ�j���������炪�m�F�A�ĉȊw���l�C�`���[�E�j���[���T�C�G���X�i�d�q�Łj��20���A���\�����B - �R�[�q�[���̊��ƌ�������h�����Ƃ�������2���̐V��������
�y2��15���z�ŋ߂̌����ł͓���I�ȃR�[�q�[�̈��p�œ��A�a��p�[�L���\���a�Ƃ��������������̃��X�N���������Ȃ�\�����w�E����Ă��邪�A����I�ȃR�[�q�[�̈��p��2��ނ̊����\�h�ł���\��������Ƃ������������\���ꂽ�B�R�[�q�[���p�������X�N�ɋy�ڂ��e���ׂ��ŐV�̌���2���͕ʁX�̂��̂ł���A�wJournalof the National Cancer Institute�x2��16�����ɔ��\���ꂽ�B(2005/07/22) - �y�J�t�F�C���z�Ȃ����C���Ȃ��Ȃ��?�u��ꂪ�Ƃ��v�͖{��?
���́@�I���v�E����������w�Љ���w������
Newton�@2009-9:112-113
�_�o�ɏ�`����,���̓ˋN���[���疖�[����uATP(�A�f�m�V���O�����_)�v��u�O���^�~���_�v�����o����,���̐_�o�ɏ���`����B�������֓`�������Ƃ̐_�o�ɂ́u�A�f�m�V���v���������ĉߏ�ɁuATP�v��u�O���^�~���_�v�����o�����̂�h���ł���.�J�t�F�C���͂��̃A�f�m�V���̌������ז�����͂��炫������B
���̂��߂ɁuATP�v��u�O���^�~���_�v�����o���ꑱ���A���̐_�o�ɑ����̎h�������������B
�J�t�F�C����,���܂��܂Ȑ_�o�ɂ͂��炫,���l�ȍ�p�݂����B�ʏ�̐ێ�ʂł����,���C���o�܂��o����p��,���A��p,���i�̎��v�͂����߂��p�Ȃǂ����邪,�ߏ�ɐێ悷��ƕs���ɂȂ�����,�s�����������ꂽ�肷�邱�Ƃ�����B
�J�t�F�C���ێ�͉����O����������
��J���▰�C���������悤�ƃJ�t�F�C�����Ƃ�̂�,�Ƃ��ɂƂĂ��L���ł���B���������ӂ��ׂ���,�J�t�F�C������J������������̂ł͂Ȃ��Ƃ������Ƃ��B���������Ȃ��悤�ɂ��Ė����ɓ�������,��J�͂�������Ƒ̂ɒ~�ς��Ă���B�I�������̂������߂̃J�t�F�C�����p�p�͒��Q�ɗ��p���邱�Ƃ��Ƃ����B�����͊m���ɔ�J��������B���H��ɃR�[�q�[������ʼn������Ƃ��,��20�����炢�ŃJ�t�F�C�����z�������B����Ɗo�����ʂɂ����,��������Ɩڊo�߂���Ƃ����B�����Ă݂Ă͂��������낤���B - ���R�[�q�[�͕č��ɂ����čR�_�������̍ő�̐ێ挹
�`�č��l�͑��̐H����������R�[�q�[����R�_�������𑽂��ێ�`
�č��l�̍R�_�������̐ێ挹
�R�[�q�[�Ɏ����ŁA�č��l�̐H���ɂ�����R�_�������̐ێ挹�Ƃ���10�ʈȓ��ɓ������͎̂��̂悤�Ȃ��̂ł������B
�E ���������Ȃ��g��
�E �o�i�i
�E ��������������
�E �g�E�����R�V
�E �ԃ��C��
�E �r�[���i���K�[�r�[���j
�E �����S
�E �g�}�g
�E �W���K�C�� - �^����̋ؓ��ɂ��J�t�F�C�����ɘa
- �^���O�ɃR�[�q�[��2�t���ނƁA���̌�̋ؓ��ɂ�50%�߂����炷���Ƃ��ł��邱�Ƃ��V�K�̌����Ŏ������ꂽ�B
- �J�t�F�C�����ł������₷���͕̂��i�J�t�F�C����ۂ�Ȃ��l��^�����Ȃ��l�ł���B
- �������ʂ́wPain�x�I�����C���ł�12��11�t���Ōf�ڂ���A����2�����Ɍf�ڗ\��ł���B
- �R�[�q�[�ێ�ɂ�茴���������z�����X�N���y��
- Coffee drinking tied to reduced risk of primary blepharospasm against blepharospasm by blocking adenosine receptors,
- J Neurol Neurosurg Psychiatry 2007 online.
- 1��4�t�ȏ�̃R�[�q�[�Ŕ]�������X�N���ቺ�H
���̌��ʂ́E�E�E���N�l�݂̂Ŕ��������
�����ł́C���M�����[�R�[�q�[�̐ێ�ʂ������قǔ]�������X�N���ቺ����Ƃ̌������ʂ�Circulation 2��16���I�����C���łɌf�ڂ��ꂽ�B
����ɂ��ƁA�R�[�q�[�ێ�ʂ�1����4�t�ȏ�Ƒ��������ł́A����1�t�����̏����ɔ�ׂĔ]�������X�N��20���ቺ�����B
�܂��A1����2�`3�t�̏ꍇ�̃��X�N�ቺ����19���C1�T�Ԃ�5�`7�t�̏ꍇ�ɂ�12���ቺ�����Ƃ����B - ��top
 ���ɂɂ悢�H�i
���ɂɂ悢�H�i
���Г��ɂ̗\�h�ɂ悢�}�O�l�V�E�������Ղ�̃n���o�[�O
- �ŏI�x���I�������̖{���͕|���ƒ�̈�w���i�Г��ɂ̗\�h�j2007�N����
- �ޗ�
- �Ђ���
- �Ђ���
- ������
- �ϊ��̕�
- �S�}
- �ʃl�M
- ��
- �P�`���b�v�A�E�X�^�[�\�[�X�A���A�Ӟ��A�i�c���O(���h��)
- ����
- �P�D��ɖ������āA�Ђ����ɂ˂肪�o��܂ł܂���B
- �Q�D�����߂��ʃl�M�A�Ƃ����A������A�Ђ����A�ϊ��̕��A�S�}��������B
- ���A�Ӟ��A�i�c���O�����X�����Ă悭�܂���B
- �R�D�`�𐮂��āA�������艷�߂��t���C�p���ŗ��ʂ���Ă��B
- �S�D�W������15����ŏĂ��B
- �T�D�n���o�[�O���Ƃ肾�����t���C�p���ɃP�`���b�v�A�E�X�^�[�\�[�X�A�������ă\�[�X�����B
- �U�D���̖�ƃn���o�[�O��t���A�\�[�X��������B
- ��top
�����N�ێ��̂��߂̐H��
�H���͕a�C�̗\�h�A���Â̍��{�ł��B
���L�͓��ɂƊW�Ȃ��A���N��ۂ��߂̐H���̒��ӂł��B
- �P�D�L�[�|�C���g
- �i�P�j���b�A�`�����A�����A�H���A�G�l���M�[�̂��ׂĂɒ��ӂ���B
- �i�Q�j���b�A�`�����͓������H�i�A�A�����H�i�̗�������ۂ�B
- �i�R�j�������H�i�͓��ɕ炸�����ۂ�B
- �i�S�j�����͕ĂȂǂ̍��ނ����ɐۂ�A�������̐ێ�͍T����B
- �i�T�j�H���͂P���P�O���ȉ��ɂ���
- �i�U�j��͂P���Q��ȏ�
- �i�V�j�����i�͖����ۂ�B
- �i�W�j�A���R�[���͓��{�����Z�łP���Q�������ɂ���B
- �Q�D�H�ׂ����̊ϓ_����
- �i�P�j�H���͂悭����ŐH�ׂ�B
- �i�Q�j�H�ׂ����Ȃ��A���݂����Ȃ��B
- �i�R�j�H���͐����̃��Y���ɂ��킹�ċK���������B
- �i�S�j�D��������������Ȃ��B
- �i�T�j�a���A�m���A���ؕ��Ȃǂ��낢��̗����`�Ԃ̂��̂�H�ׂ�悤�ɂ���B
- �i�U�j�M������H���A�����͉ߓx�ɐۂ�Ȃ��悤�ɂ���B
- �R�D�h�{�ێ�̊ϓ_����
- �i�P�j�G�l���M�[�͎����̂��炾�Ɗ����ʂɂ��킹�Đۂ邱�ƁB�i�W���̏d���ێ����邱�Ɓj
- �i�Q�j�`�����͏\���ɐۂ邱�ƁA�������`�����̐ێ�䗦�́A�����ނ˂T�O�����x�Ƃ��邱�ƁB
- �i�R�j���b�͐ۂ肷���Ă��s�����Ă��悭�Ȃ��B
- ���ێ�G�l���M�[�̂Q�O�|�Q�T�����]�܂����B
- �O�a���b�_�̊����͑����s�O�a���b�_�Ɠ��������A��⏭�Ȃ߂ɂ���B
- �i�S�j�Y�������͑��ێ�G�l���M�[�̂T�T�`�U�O�����]�܂����B
- ���̒��ŁA�����ނ̊����͂ł��邾�����Ȃ����A�ł�Ղ�@�ۂ̊����𑽂�����B
- �i�T�j�i�g���E���͐H���Ɋ��Z���ĂP�O���ȉ��ɂ��邱�ƁB
- �i�U�j�J���E�����\���ɐۂ�B
- �i�V�j�~�l�����ƃr�^�~���͏\���ɐێ悷�邱�ƁB
- �S�D�H�i�ێ�ʂ̊ϓ_����
- �i�P�j�P���ɂR�O��ވȏ�̐H�i��ۂ�悤�ɐS�����邱�ƁB
- �i�Q�j�哤���i�܂��͋��ނ��P���P��Ƃ�ۂ�悤�ɂ��邱�ƁB
- �i�R�j�Ή��F����P���P��͐ۂ邱�ƁB
- �i�S�j�����A�����i��ۂ�悤�ɂ��邱�ƁB
- �i�T�j���ނƋ��ނ͂قڔ��X�ɐۂ�悤�ɂ���B
- �i�U�j�����g�������ł͐A�������悭�g���悤�ɂ���B
- �i�V�j�������̑����H�i�͐ۂ肷���Ȃ��悤�ɂ��邱�ƁB
- �i�W�j�H���̑����H�i�͍T���ڂɂ��邱�ƁB
- �i�X�j�H���̐ێ�ȏ��Ȃ����邽�߁A�Ȃ�ׂ��������ɂ�����A���h���̎g�p�Ȃǂɂ�閡�����H�v����B
- �i10�j�A���R�[���͓K�ʁi�P���Q�����x�܂Łj�ɂƂǂ߂邱�ƁB
- ��top
���Г��ɂɂ悢�H�ׂ���
- �Г��ɂ͖����������Ƃ��ă}�O�l�V�E����₤�Ƃ悢�B
- �}�O�l�V�E��������Ȃ��ƕГ��ɂ�������₷���Ȃ�܂��B
- �Г��ɂ̂ЂƂ́A�Ή��F���t����̐ێ悪�s�\���Ȃ��߁A
�}�O�l�V�E�����s�������Ƃ����Ă��܂��B - �Г��Ɋ��҂�30�`50���̓}�O�l�V�E�����s�����Ă���Ƃ����f�[�^������܂��B
- ���̂悤�ȏꍇ�A�ΐH���Ȃ����Ƃ悢�ł��傤�ˁB
- ���킵���́��}�O�l�V�E��
- �o�T�FMedical Tribune 1999.8.26
- �Q�l�@�������Ɋ��҂͗Ή��F��A���A�哤���i�̐ێ悪�L�ӂɏ��Ȃ��B
�|������v�ق�(�����w��w���]�]�_�o����): �Г��ɂ̗L�a����QOL:���挧��R���ɂ�����S�Z�������B���{���Ɋw�� 2002;29(1):66-68��� - ��top
- �q�W�L�͓��ɂɂ悢�Ƃ����Ă��܂��B�������p���H�i�K�i���iFSA�j�͂V��28���Ɂu�Ђ�����H�ׂ�ׂ��łȂ��v�Ɗ������܂����B
�Ȃ��Ȃ炲���ʂ���f���ӂ��܂�邩��ł��BMedWave�́A2004.8.2�t���̋L���Łu�D�P�����ƂR�Ζ����̎q�ǂ��̓q�W�L��H�ׂ�ׂ��łȂ��A���̑��̐l���T�ɏ����P�t�܂Łv�ihttp://medwave2.nikkeibp.co.jp/wcs/leaf?CID=onair/medwave/tpic/323166�j�Ƃ̃R�����g�\���Ă���܂��i2004.10.12�j�B
- �H���Ö@�̌���Ł��Г��ɂ�MBT�ɂ�鎡��
- ���r�^�~���a2�Ö@�i�r�^�~���a�Q�̑�ʐێ�͕Г��ɂ����P������j�A
- ���i�c�V���M�N
- ���C�`���E
- L-�g���v�g�t�@��
- ����
- ��top
���哤
- �C�\�t���{���͑哤�ɑ�ʂɊ܂܂�܂��B
- �C�\�t���{���͍ŋߏ����z�������̃G�X�g���Q���Ǝ������������܂��B
- �Г��ɂ��N����ɂ������܂��B
- �q�{����A������̃��X�N�ጸ���܂��B
- �R���X�e���[����ቺ�����܂��B
- ���e頏ǂ�ቺ�����܂��B
- �X�N����Q���y�������܂��B
- �C�\�t���{���̐ێ�ʂ͈����40mg�`50mg�����z�ł��B
- �����Ȃ�150g�i�����j�A���ȕ��Ȃ�20g�A�[���Ȃ�60g�i�P�p�b�N�j�ł��B
- ��top
 �Q�l
�Q�l
���R�J�E�R�[��
- 2011�N5��8���̓R�J�E�R�[����125�̒a�����ł��B
- 125�N�O��1886�N�ɕăW���[�W�A�B�A�g�����^�̖�t�W�����E�y���o�[�g���́A
�u�r���E�}���A�[�j�v���Q�l�Ƃ��āA
���ɂƔ�J���ɘa����u�R�J�E�R�[���v�Ƃ����������V�s��n�Ă��܂����B - �u�r���E�}���A�[�j�v�̓��C���ɃR�J�C���̐�����n��������p���ŁA
�G�W�\����[�}�@�����������Ă��܂����B - ���̌�A�R�J�C�����������������A������ς��Ȃ��獡�Ɏ����Ă��܂��B
- �R�J�R�[���ɂ̓J�t�F�C�����܂܂�Ă�̂ŁA�������ɓ��ɂ��Ƃ��p������܂��B
- ���������݉߂��ɂ͒��ӂ�(�J�t�F�C�����߂�����)
- ��top
- �Г��ɂ͐H�~�������ُ̈�ɋC�Â����Ƃ�����
- �f���C�ƚq�f�͑����̊��҂Ɍ�����
- ���ɂ≺�����N���邱�Ƃ�����
- �H�~���ُ혴�i���邱�Ƃ��A�ቺ���邱�Ƃ�����
- �Â����́A���Ƃ��`���R���[�g(�Г��ɗU������)��H�ׂ����Ȃ邱�Ƃ�����
- �֔��i���邱�Ƃ�����
- �f���C�̌���(����)
- �Z���g�j���̂���
- �Z���g�j���̂X�T���͒��ǂɊ܂܂��
- �Z���g�j���͒��ǂ̓����i����
- �J���`�m�C�h�Ƃ�����ᇂ͉�������Ǐ�Ƃ��邪�A����͑�ʂ̃Z���g�j�������
- �Г��ɂ͑̓��̒����ꏊ����Z���g�j�������o�����
- �Z���g�j���ɂ�蒰�ǂ̓���������������Ƃ���ɃZ���g�j�������o�����
- �Г��ɂ͑̓��ɐ�������������B�w�ւ������Ȃ�A��E�����ނ���
- �Г��ɂ����܂�Ƒ�ʂ̔����A���r�o�����
- ��top
��Spierings�@ELH/���{����u�Г��ɂ̎��Áv1997���
- �H��(n=500) Peatfield RC et al 1984
19���̓`���R���[�g�����炩�ȗU���v��
18���̓`�[�Y
11���͊��k��
29���̓A���R�[�� - �Г��Ɋ��҂ɑ��钲��(n=429)Peatfield RC 1995
16�����`�[�Y���邢�̓`���R���[�g�ɂ���ē��ɂ������i�����͋��ʂ��ėU���j
18���̊��҂ł̓A���R�[�����܂ނ���������œ��ɂ�����
12���̊��҂͔����C��OK�A�ԃ��C���œ���
28���̓r�[��
�`�[�Y��`���R���[�g���ƁA���C����r�[�����͖��炩�ȑ��ցB
�H���Ɋւ��銴�ƁA�A���R�[�����ɂ͑��֊W�Ȃ� - ���ɔ�����N�����O24���Ԃ̈��ݕ��ƐH�ו��ɂ���3�����Ԃɂ킽���Ē���
�Г��ɂ�L����1,883��̏����A���P�[�g���� Dalton K 1975
���v2�A313��̓��ɔ���̂���
40���`�[�Y�̐ێ�
33���`���R���[�g
23���A���R�[���A
21�����k��
67����H - ��H�ɂ��U�����ʂ́A�ጌ���ɂ����̂ł͂Ȃ�Pearce J 1971�D
�C���X�����̒��˂ō��x�̒ጌ���ǁi�����l��20mg�^100ml�j�ɂ��Г��ɂ��N�������̂�2/20�Ⴞ�������� - �n���`�[�Y�A
�`���~���i�`���R���[�g�Ƃ͈قȂ鐶���w�I�A�~���j���Y������D
�������͂�A�J�e�R�[���A�~���������_�o�I�������o�����O�������k���A���Ƃœ��ɂ������N��������D - �`���~��
��d�ӍZ��r���� Ziegler DK Neurology 1977;27:725-726.
25���i�`���~���j�F29���i�v���Z�{�j�œ��Ɍ��ʂ͂Ȃ����� - ���k��
�I�N�g�p�~�����܂�ł���B
���̃A�~���͌����_�o�I���ŃJ�e�R�[���A�~���ɒu������� - �H�i�Y����
���Ɏ_���A�O���^�~���_�i�g���E���A�A�X�p���M���_�����ɂ��N�����B
�Y�����ɂ���Ĉ����N������錌�NJg��
�����_�o�n���h���������ʂƂ��Č��ǎ��k���������B
���ɂ͌����_�o�n�̊��������ቺ���A�������Ɍ��NJg�����N�����Ƃ��ɐ����� - ���Ɏ_��
���ɑ��ĐԐF��ۂ��߂ɓY������A
�t�����N�t���g�\�[�Z�[�W�A�x�[�R���A�T���~����уn���Ȃ�
���Ɏ_���͌��NJg����ŁA���^30���ȓ��Ɋ�ʔ��Ԃ��� - �O���^�~���_�i�g���E��
���ؗ����̑f�ނɑ��ʂɗp�����Ă���B
���ǎ��k��p��L����
���̌��ǎ��k���ʂ��`���~���ɂ���ċ��߂���D - �A�X�p���M���_
�l�H�Ö����ŁA�������150�`200�{�Ö��������A�_�C�G�b�g�H�i�Ɏg�p�����D
�A�X�p���M���_���U���v���̗Ⴀ�� - �J�t�F�C��
���ǎ��k����
�R�[�q�[�k��250m��������50�`100mg�l
�g���k��250m��������25�`50mg
�R�[���k350m��������15�`25mg�l
�J�t�F�C���͑̓������������Ƃ��ɓ��ɂ������炷�D
�J�t�F�C���̋֒f�Ǐ�͂悭�T���ɋN���₷���B
�Q�߂��ɂ��R�[�q�[�����p���x��邱�Ƃ���������D - �T�����ɂ̃A���P�[�g�����in=101�j
30���͏T���ɓ��ɔ��삪����
�T�����Ɋ��҂�1�������肻��ȊO�̊��҂̖�2�{�̃J�t�F�C����ێ悵�Ă���
�T�����Ɋ��҂̃J�t�F�C���̕��ϐێ�ʂ�1��������734mg�i510�`1253mg�j
�T�����Ɋ��҂͓y�j������j���ɕ���1.8���ԁi30���`3���ԁj�����Q�Ă���D - ��top
���n���E�\�[�Z�[�W�͓��ɂ̌����ƂȂ邩
- ���_�u�Ȃ�Ȃ��v
- �u�n���E�\�[�Z�[�W�E�T���~�����ɂ̌����ƂȂ�v�Ɠ��ɂ̖{�ɏ����Ă���܂�
- ������z�b�g�h�b�N�����Ƃ����܂�
- ���̍����͊O���̕����̎���ł�
- ���ɂ̌����͂����Ɋ܂܂��Ɏ_���i���ǂ��L�����p������B���S�ǎ��Ö�Ɏg���Ă���j�̂��߂��Ƃ���Ă��܂�
- �������킽�����̌o���ł́A�H���œ��ɂ��N�����Ƃ����b�����ۂɂ͂��������Ƃ�����܂���
- �����Ŗ^�n�����[�J�ɍ����H���ɍ����Ɏ_�����g���Ă���̂������₵�܂���
- �킩�������Ƃ͓��{�̃n���̏Ɏ_���g�p�ʂ͊O���������Ȃ������ɁA
���ɓ���i�K�ł͎c���ʂ͂���߂ď��Ȃ��A
�ނ�������̂ق��̐ێ�ʂ��������炢�ł���A
���������ē��ɂ̌����Ƃ͂Ȃ�Ȃ����낤�Ƃ������Ƃł� - ���Ɏ����̕������S���ăn����\�[�Z�[�W��H�ׂĂ�������
- ��top
���⑫
- ���Ɏ_���̎g�p�ړI��
���F�ƕ����̏����A�h���̎O�_�ł��B - �n����\�[�Z�[�W���̐H�����i�̐����H���ɂ͉��́i�����j�Ƃ����H��������A
���̍H���ł͌����H���ɐH���Ɣ��F�܂�Y�����ė①���A
�n�������ُ���������ƂƂ��ɓ��F�F�����܂��B - ���̔��F�܂Ɉ��Ɏ_�����g�p���܂��B
- ����͒��F���̂悤�ɐF��t����̂ł͂Ȃ��A�����̐F�f���Œ肵�A��F��h�����̂ł�
- ��̓I�ɂ́A���Ɏ_�\�[�_��H���ɓY������ƁA
�����_���邢�͓��_�̍�p�ŗV���̈��Ɏ_�iHN02�j�ƂȂ�A
����ɊҌ�����Ď_�����f�iNO�j�ƂȂ�܂��B - ����NO���A�~�I�O���u�����i���̐F�f�j��w���O���r���i���F�f�j�ƌ������āA
�j�g���\�~�I�O���u�����iMbNO�j�A�j�g���\�w���O���r���iHbNO�j�ƂȂ�F�f���Œ肳��܂��B - ���������Ĉ��Ɏ_�\�[�_�͔��F�܂Ƃ������͐F�f�Œ�܂ƌĂԂ̂��������悤�ł��B
- ���Ɏ_���ɂ͍ۂ̑��B��}���铭��������܂��B
���ɁA�ł����낵���H���ŋۂł���{�c���k�X�ۂ̑��B�}�����ʂ�����܂��B - �Ȃ����Ɏ_���̔������͂��܂ł͔ے肳��Ă��܂��B
- ���Ɏ_���́A�H�i�q���@�ɂ��c�����Ƃ��āu70ppm�ȉ��̊�v������܂��B
���̊�͏��O���ɔ�גႭ�Ȃ��Ă��܂��i�č��ł̓\�[�Z�[�W100ppm�j�B
X�Ђł́A���̔�����35ppm�ȉ�����Ƃ��Ă��܂��B - ����ɐH�����i�̈��Ɏ_�c��́A��������Ă���ŒZ���Ԃ̊ԁi1�T�Ԉȓ��j��10ppm�ȉ��Ɍ������܂��B
���M�ł���ɂ��̉ߒ��͑��i����܂��B - ���ǁA���Ɏ_���͓��ɂ��N�����قǂ̗ʂɂ͂Ȃ肦�Ȃ��Ǝv���܂��B
- �����F�z�b�g�h�b�N���ɂ̏��o�_��
Henderson WR, Raskin NH: "Hot-dog" headache: individual susceptibility to nitrite. Lancet 12.2:1162-1163, 1972 - 1999.12.15�f��
- ��top
�����Ɏ_���E�Ɏ_��
- ���Ɏ_�͐��n�t�Ƃ��Ă������݂��A�ア�P����_�ł���B�������������Ɨe�Ղɕ������āA�_�����f����Ɏ_����B
�R�g�m�n2�@���@�g�m3�@�{�@�Q�m�n�@�{�@�g2�n - ���Ɏ_�͊Ҍ��܂ɑ��Ď_���܂Ƃ��č�p���A�܂��_���܂ɑ��Ă͊Ҍ��܂Ƃ��č�p���Ɏ_�ƂȂ�B
- �H�����̈��Ɏ_
NO2-(ppm)�@
�����i�F�E�C���i�[�\�[�Z�[�W�@�@�@12�`80
�v���X�E�n�� �@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@14�`29 - �Ɏ_�J���E��(KNO3 )�A�Ɏ_�i�g���E��(NaNO3 )�A���Ɏ_�i�g���E��(NaNO2 )�̌`�œ����i�̔��F�܂Ƃ��Ďg�p����Ă���B
- �H���ނ̃~�I�O���r���A�w���O���r���Ȃǂ̐ԐF�F�f�́A�_�����ă��g�~�I�O���r���A���g�փ��O���r���Ȃǂ̊��F�F�f�ɕό^����B
- �w���O���r����~�I�O���r���͈��Ɏ_�����琶�����_�����f�i�m�n�j�ƌ������āA
�������ԐF�̃j�g���\�w���O���r����j�g���\�~�I�O���r�����A
���̓��ԐF��ێ�����B - �Ɏ_���������̎_�f�Ȃǂɂ��Ҍ���p���Ĉ��Ɏ_�������l�ɍ�p����B
- �o�T:���ۊw�@��ʒZ����w�E���ƌ����_�����^�W�E�Ɏ_�E���Ɏ_�Ɋւ��錤�����
- ��top
��L-�g���v�g�t�@��
- �Г��ɂ͔]���̃Z���g�j���̌��R�ƊW������Ƃ����Ă���
- �]���āA�Z���g�j���̑O�앨���ł���L-�g���v�g�t�@���͕Г��ɂ̗\�h�ɗL�]��������Ȃ�
- �����P
- �X�^�C���F��d�ӌ��N���X�I�[�o�[�@
- �ΏہF���Ò�R���Г��Ɋ���8�l
- ������F6���Ԃ��Ƃ�500mg��L-�g���v�g�t�@��/�v���Z�{�iL-���C�V���j
- �������ԁF�R������
- �����F���ϓ��Ɏw���i����~���십�x�j
- ���ʁFL-�g���v�g�t�@���̕����v���Z�{�ɔ�ׂ�32.8���Ⴉ�����ins�j�B
���Ɏw����L-�g���v�g�t�@�����Ò��͊���8�l��4�l�Ńv���Z�{�ɔ�ׂĒ����ɒႩ���� - ���_�FL-�g���v�g�t�@���������̕Г��ɂɈ��̉��l��L����\���̂���
- �����Q
- ��d�ӌ�����
- �ΏہF�Г��Ɋ���
- ������F3g/day��L-�g���v�g�t�@���^�v���Z�{
- �������ԁF1������
- ���ʁFL-�g���v�g�t�@���Q60�l�̓v���Z�{�Q�ɔ䂵�Г��ɂ��L�ӂɏ��Ȃ��������Ԃ��Z������
- ���̏�����L-�g���v�g�t�@�����Г��Ɋ��҂̈ꕔ�ɑ��Ă͗\�h�I���l�������Ă��邱�Ƃ��������Ă���B�@
- L-�g���v�g�t�@���͏d��ȕ���p���Ђ��������Ƃ͕���Ă��Ȃ��B�i�s�����̍�������L-�g���v�g�t�@���͊댯�j
- ������L-�g���v�g�t�@���͒��ܖ�ǂ������\�ł���i���{�ł͕s�\�j
- �o�T: �~�O�����[�u�̃T�C�g����̈��p�ł�
- ��top
������
- �Г��Ɋ��҂́A������Ԍ������̃I���K-3���b�_�̔Z�x���L�ӂɒႢ
- �I���K-3���b�_�͎�Ƃ��āA�����A�A�}�j���A�����A�����E�̎����Ɋ܂܂��
- �I���K-3���b�_�͌����̋ÏW��j�~����
- ���̍�p�ɂ�茌���̃Z���g�j�����o�����������A����ɂ͔]�����̝��k�ƕГ��ɂ̔�����y��������
- ����
- �X�^�C���F�����_����d�ӌ��N���X�I�[�o�[�@
- �ΏہF�Г��ɖ�ɔ������Ȃ��Г��Ɋ���15�l
- ������F�����Z�k���i�A�����j�^�v���Z�{
- ���^���ԁF6�T��
- ���ʁF���ϓ��ɋ��x��L�ӂɒቺ
- ����p�F�ݒ��Ǐ�
- ��top
�����H�K��
- ���H�͕Г��ɂ̂��Ƃł��B����l�͌��H����l�������̂ł��ˁB
- �قƂ�ǖ������H�@�T2-5�H
- 15-19�@ 9.8/ 6.9 11.5/12.5(�j/����)
- 20-29�@�@23.4/13.6 22.9/21.1
- 30-39�@�@20.8/ 9.3 18.0/15.7
- 40-49�@�@12.0/ 6.8 12.6/ 8.6
- 50-59�@�@ 9.0/ 5.7 10.2/ 7.3
- 60-69�@�@ 4.0/ 2.9 5.2/ 4.0
- >70 �@�@ 4.5/ 2.9 2.5/ 4.5
- �o�T(SCOPE 2003;42:26)
- ��top
���H���̐ێ�p�x�@��R���̏Z������(�����w)
- �`�Г��ɂƋْ��^���ɂ̎ҁA���ɂ̂Ȃ��҂Ƃ̊ԂŁ`
- ������̕a�^
- ����哤�H�i�̐ێ悪���Ȃ�
- �������̐ێ悪����
- ����
- �Ή��F��ƊC���ނ̐ێ悪�L�ӂɏ��Ȃ�
- �R�[�q�[��g���̐ێ悪�L�ӂɑ���
- Medical Tribune [2003�N8��7�� (VOL.36 NO.32) p.22]
- ��top
�����Ƒ����������̂́H
- ���ɂ́A�q�X�`�W���������܂܂�Ă��܂��B
- �q�X�`�W���͒����ۂɂ���ăq�X�^�~���ɕω����܂��B
- �q�X�^�~���̓A�����M�[�̂��ƂɂȂ�܂��B
- �q�X�^�~���𑽗ʂɐێ悷��ƃA�����M�[�l�̐H���ŁA����܂���A�݂����悤�Ȃǂ������N�����Ƃ������Ă��܂��B
- �����̋��ƁA�R����⌋�j���Ö���ꏏ�Ɏ��ƁA�̓��Ƀq�X�^�~�����~�ς��ăq�X�^�~�����łɂȂ�܂��B
- �Ǐ�Ƃ��Ă͓��ɁA���]�A�f���C�A�����A�����Ȃǂł����A�Ђǂ����ɂ͊�@�I�ȏɊׂ邱�Ƃ�����܂��B
- �m���g�����A�A���L�T���A�g���t�j�[���A�g���u�^�m�[���A�e�g���~�h�Ȃǂp���Ă��銳�҂���́A���ꂮ������ӂ��Ă��������B
- �X�`�W���ܗL�ʂ͍��������珇�ɁA�}�O���A�u���A�n�}�`�A�T�o�A�T���}�A�C���V�B�����ł́A�T���}�A�C���V�A�A�W�̏��ɂȂ�܂��B
- ���� ���@�s�̖�̊댯�u�H���킹�v ���
- �H���łɂ�铪�Ɂi���s�V���j
2008-03-13�����ɐH���ŏo���ꂽ�}�O���̃o�^�[�Ă���H�ׂ��j���ɔ��]�⓪�ɂȂǂ̏Ǐ���A
�}�O������A�����M�[�⓪�ɂ̌��������q�X�^�~�������o���ꂽ�Ƃ������Ƃł��B
- �\�H�����ݍ�p�ɂ�钆�� �\�R���j��q�h���W�b�h�Ƌ��i�J�W�L�j�ɂ��q�X�^�~�����ł̌o������\
- ���j�a�����@����29�̏����͒��H��13���ʂ��� �u���Â��ł������ꂽ�悤�ȁv���邢�́u��������悤�Ȓɂ��݁v�����ǂ����B
- ���ɂ̂ق��ɁA��ʍg���A�����������ł������B
- �H��30���ʂɂ͈��S�E�q�f���o�����A�_�o�w�I�ُ폊���͔F�߂��Ȃ������B
- CT�ُ͈폊���͖��������B
- ���̃q�X�`�W�����ۂɂ��q�X�^�~���ɕω�����B
- �R���j��INA��MAO�}����p�����邽�߂ɑ̓��q�X�^�~���̒~�ς�������q�X�^�~�����ł��N���������̂ł���B
- �q�X�`�W�������Z�x�Ɋ܂ރ}�O���A�T�o�A�C���V�ȂǐԂ݂̋��ɗv���ӂł���B
- �R�q�X�^�~����ŗ\�h�\�ł���B
- �O�㗝��Y�ق����{�㎖�V�� No�D3235�i��61.4.26���j;26-32(�x���q�q�搶��)
- ��top
- ����g����H�ׂē��ɂ��o���I�H
2014/8/22
�@���j�a����މ@����40�Α㋛��D���j�����O���Ɍ����܂����B�u�����A���@���ɐH���Ȃ�������g��������ł������Ă������炢�H�ׂ���₯�ǁA�����ɂ��Ȃ��ċ����^���ԂɂȂ�������B���䂭�Ă��䂭�āv
�@���j���Ö�̃C�\�j�A�W�h�i���i���C�X�R�`�����j��������Ă��銳�҂��}�O����J�c�I�Ȃǂ̃q�X�`�W���𑽂��ܗL����Ԑg����H�ׂ�ƁA�q�X�^�~�����Ő����ɂ��₷���Ȃ�܂��B�C�\�j�A�W�h�́A�`�[�Y�⋍���Ȃǂ̓����i�A�r�[���A���C���A���o�[�Ƃ������`���~���̑����H����H�ׂ邱�ƂŁA���ɁA�����㏸�A�������N�������Ƃ�����܂��B
�o�T�@http://medical.nikkeibp.co.jp/inc/mem/pub/blog/kurahara/201408/537524.html - ��top
 ����
����
- New onset migraine associated with use of soy isoflavone supplements
Peter A. Engel Neurology 2002 59: 1289-1290.
